
毎回勉強させてもらっているkintaのブログで紹介された
特総研報告書
重複障害児のアセスメント研究 実践につなげやすい重複障害のある子どもの見え方とコミュニケーションに関する初期的な力のアセスメントガイドブック(試案) 専門研究A【重複障害児のアセスメント研究-視覚を通した環境の把握とコミュニケーションに関する初期的な力を評価するツールの改良-】を読ませてもらい、3学期の授業を考えるうえで、とても参考になりました。
その中で大事だと思ったところをM.M化してみました。
ちっちゃくて見えませんが画面をクリックすると大きくなります。
子どもとのコミュニケーションで12の支援ポイントのうち
コミュニケーションが成立するための基本要素を保障する支援として八個かかげられていました。
(1) どこ?が分かること
(2) なに?が分かること
(3) だれ?が分かること
(4) だれから離しかけらてるか?
(5) 子どもへの分かりやすいフィードバック
(6) 始まりと終わりが分かるようにすること
(7) 感覚刺激の調整
(8) 活動の予告
子どもが興味を持つ教材を一生懸命作っても、障害が重ければ、重いほど、授業においての環境設定を大事にしないと、せっかくの教材が生きてこないだということがよく分かりました。




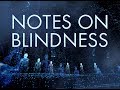



0 件のコメント:
コメントを投稿